知研ボックスS-18期【お話の構成】は、ストーリーのつながっているカードを正しいお話の順序になるように並べ替える取り組みをとおして、読解力や文章の構成力をやしないます。
こちらの記事では、【お話の構成】自宅での効果的な取り組み方をご紹介します。
知研ボックス【お話の構成】でやしなわれる能力とは
概念による受容的思考力・集中的思考力
●受容的思考力とは:外部からの情報を正しく受け取る能力・理解力
●集中的思考力とは:2つ以上の情報から1つの結論を導き出す能力・論理力
※関連記事:知研ボックスで伸ばせる24の知能因子とは

知研ボックスで伸ばせる24の知能因子とは
「知研ボックス」は、心理学者ギルフォードの知能因子論をベースに、知能研究所の創設者である肥田 正次郎が提唱した『知研式知...
知研ボックス【お話の構成】自宅での効果的な取り組み方
【お話の構成】は、ストーリーのつながったカードが7セット、全36枚を用います。
各ストーリーは、カード3~7枚で構成されています。
ストーリーのつながっているカードをバラバラに渡し、正しいお話の順序になるようにカードを並べかえさせます。
文の並べ替えで意識するポイントは以下のとおり。
●順序をあらわすことば
「はじめに」「つぎに」「さいごに」など。
●接続詞(つなぎことば)
「そして」「だから」「でも」など。
接続詞の意味と、前後の文のつながりを考える●指示語(こそあどことば)
「この・その・あの」「これ・それ・あれ」など。
指示語の内容を示す文は、指示語を含む文の前に来る。
「はじめに」「つぎに」「さいごに」など。
●接続詞(つなぎことば)
「そして」「だから」「でも」など。
接続詞の意味と、前後の文のつながりを考える●指示語(こそあどことば)
「この・その・あの」「これ・それ・あれ」など。
指示語の内容を示す文は、指示語を含む文の前に来る。
●時間の進み方
「朝・昼・夕」など時間をあらわす言葉や作業の手順など。
時間の進み方に注目して、前後関係を考える。
並べかえたら、始めから声を出して音読させ、正しく並べられているか確認させます。
その上で、子どもが並べたとおりの順番で読んで聞かせてあげ、あらためて正しく並べられているか確認させましょう。
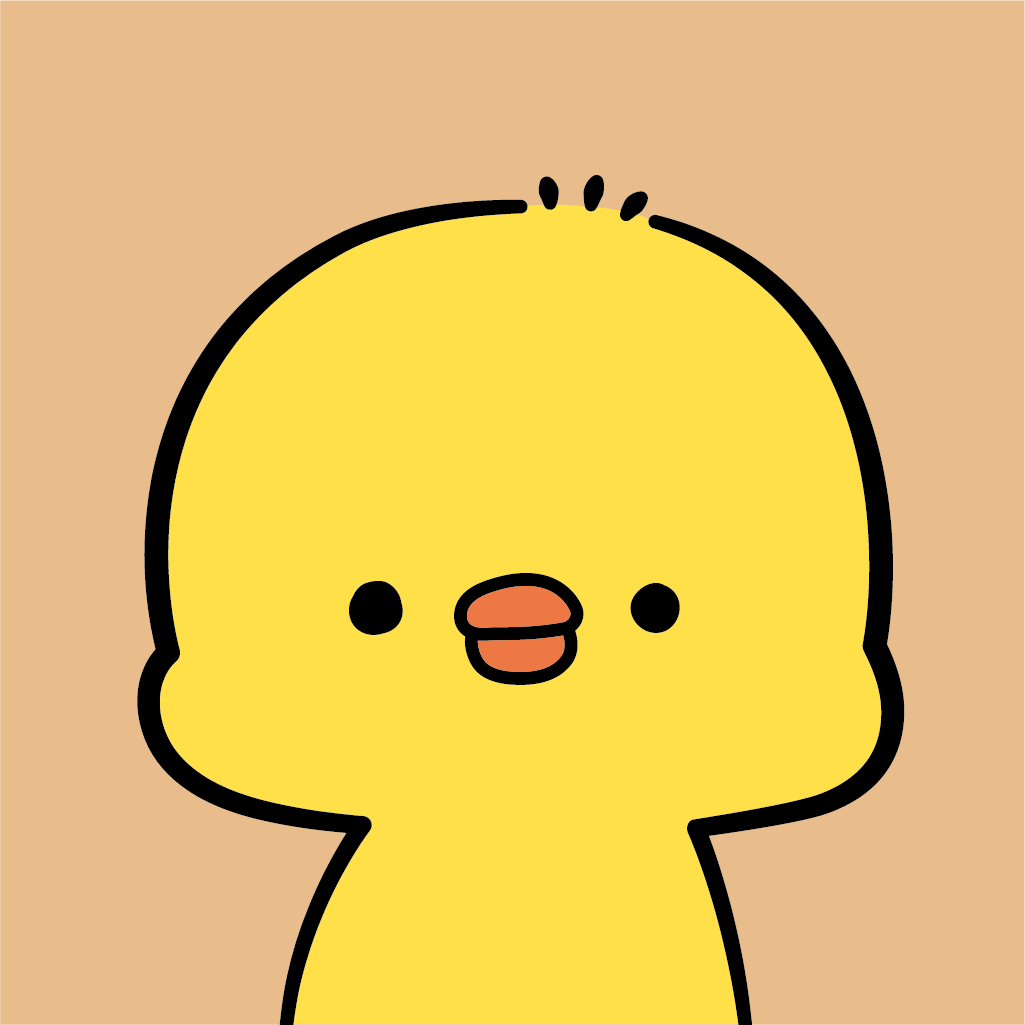
ちみに
自分で読みながら確認するのは、読み上げられるのを聞いて判断するよりもむずかしくなります。
文章の理解力・構成力の養成の課題になります。
※他にも、知研ボックスS期の教材についてご紹介しています>>>

S期(6~7歳)記事一覧
「S期(6~7歳)」の記事一覧です。
※知研ボックス 自宅での効果的な取り組み方まとめはこちら>>>

知研ボックス 自宅での効果的な取り組み方まとめ
知能研究所の教材『知研ボックス』の自宅での効果的な取り組み方に関する記事を、各期ごとにまとめました。
D期(2~3歳向...



コメント